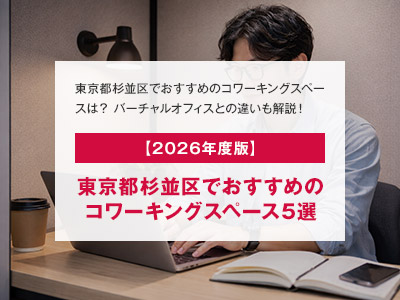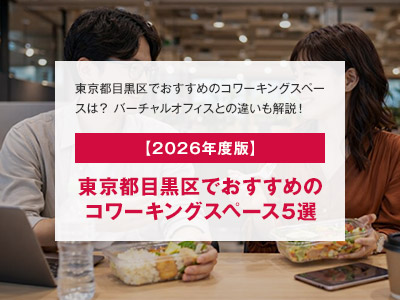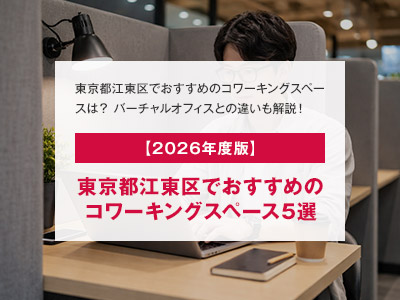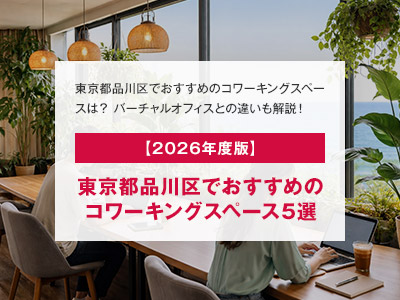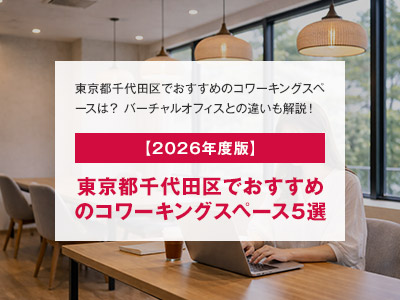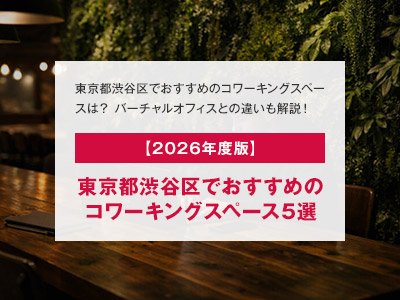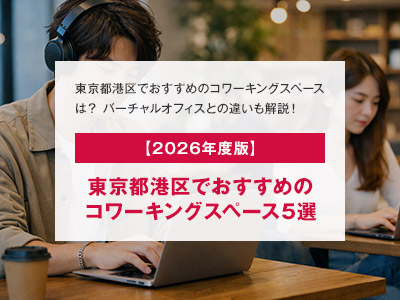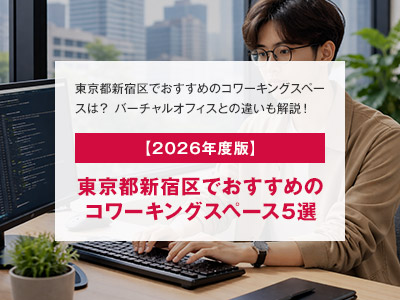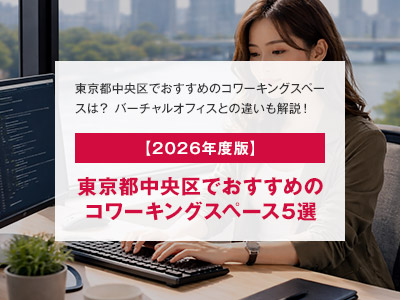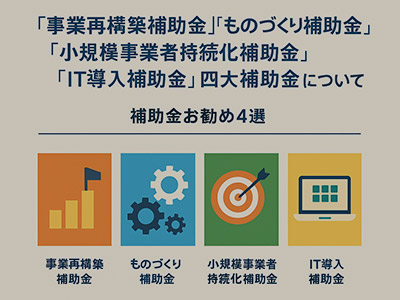古物商許可とは?申請手順や必要書類、注意点をチェック

SDGsへの取り組みが活発化しているなか、中古品の販売によって収益を得るリユー
ス販売事業が人気を集めています。
中古品の売買にあたっては「古物商許可」が必要なケースと不要なケースがあるた
め、「自分の場合はどうなのか」と疑問を抱いている方もいるでしょう。また、
「許可」といった響きから複雑な手続きをイメージし、不安を感じている場合もあ
るかもしれません。
そこで、今回は古物商許可の概要と申請手順を詳しくまとめました。また、自宅を
拠点にリユース販売事業を展開したい方に向けて、法人登記可能な住所を手軽にレ
ンタルできる「バーチャルオフィス」の魅力についても併せてご紹介します。
リユース販売事業に興味をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
古物商許可とは
古物商許可とは、古物営業法で定められている中古品(古物)をビジネスとして売
買または交換する際に必要な許可のことです。個人・法人を問わず、営利目的で継
続的に古物を取り扱う場合は必ず許可を取得する必要があり、許可を得ずに古物営
業を行った場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性が
あります。
なお、古物営業法では「古物」を次のように定義しています。
・一度使用された物品:本来の目的に従って一度でも使用された物品のことを指し、
自分自身が使用した物も該当します。
・使用されない物品で使用のために取引されたもの:使用する目的で購入または取
引されたものの、一度も使用されていない状態の物品がこれに該当します。つまり、
販売される際に一度でも消費者の手に渡った物品は、たとえ新品であっても古物に
含まれることになります。
・上記の物品に対して幾分の手入れが施されたもの:ここでの「幾分の手入れ」と
は、物品のもともとの使用目的や性質を変更しない形で行われる修理やメンテナン
スを指します。たとえば、美術品においては表面の補修がこれに該当します。
古物商許可が必要となるケース
古物商許可が必要となるケースは、具体的な取引の内容によって決まります。ここ では、代表的な6つの取引について押さえておきましょう。
1.古物を買い取って販売する場合
中古品を仕入れて販売する業態は、古物商において最もオーソドックスな営業形態 です。リサイクルショップや中古車販売店などがこのケースに該当します。
2.買い取った古物を修理して販売する場合
中古品を買い取ったあと、修理やクリーニングを施して販売する場合も古物商許可 が必要です。たとえば、中古家電を修理して販売する業者がこれに該当します。
3.買い取った古物の一部を販売する場合
中古品を買い取り、部品を取り出して販売する場合も許可が必要です。例えば、中 古パソコンを分解して部品を販売する業者が当てはまります。
4.古物を委託販売する場合
他者から中古品を預かり、販売後に手数料を受け取る形態の委託販売も古物商許可 が必要です。たとえば、フリーマーケットやオークションなどの代行業者が該当し ます。
5.買い取った古物をレンタルする場合
古物を買い取ってレンタルする場合も許可が必要で、中古のカメラや楽器をレンタ ルする業者が主な事例です。
6.国内で買い取った古物を海外で販売する場合(輸出)
日本国内で仕入れた中古品を海外で販売する場合も古物商許可を取得する必要があ
り、たとえば海外向けの中古車輸出業者が該当します。
なお、古物営業法は盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗やその他の犯罪
を防止する目的で定められた法律であることから、下記に該当する場合には古物商
許可は不要とされています。
・自分の不要品を売る場合(例:メルカリなどのフリマアプリで自分の服や家具を
販売する場合)
・無償で譲り受けたものを販売する場合(例:知人からプレゼントされた物品を販
売する場合)
・新品を購入して販売する場合(例:店舗やメーカーから直接的に新品の商品を仕
入れて販売する場合)
・自分が海外で購入した中古品を国内で販売する場合(他者が海外から持ち込んだ
ものを仕入れて販売する場合は許可が必要)
・消費してなくなる品物を販売する場合(例:食品や化粧品、薬品など)
古物商許可申請の流れ
古物商許可を取得するための申請手続きは、基本的に以下のステップに沿って進め
ていきます。
1.申請要件の確認
2.個人・法人区分の決定
3.取り扱い品目の決定
4.警察署への事前相談
5.必要書類の準備
6.書類の提出
7.審査
8.許可証の交付
具体的な手順について、以下で詳しく見ていきましょう。
1.申請要件の確認
古物商許可が必要な場合、まずは自分の状況が許可を得られるかどうかを確認する
ことが大切です。具体的には、次のような欠格要件に該当していないことが求めら
れます。
・破産者で復権を得ていない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・住居の定まらない者
・古物営業許可が取り消されてから5年が経過していない者
・暴力団員、元暴力団員、または暴力的不法行為をする恐れのある者
・公務員
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施できない者
・18歳未満の未成年者
・外国籍で適切な在留資格がない者
なお、古物商許可を得るためには営業所を用意する必要があり、営業所は「営業の
実態を確認でき、独立管理可能な個室の事務所」でなければなりません。この条件
をクリアしていれば自宅の住所を営業所として申請しても問題ありませんが、自宅
が賃貸物件や公営住宅の場合は管理規約等の関係で申請できない可能性があります。
自宅=営業所でも問題ないかどうか、あらかじめしっかりと確認したうえで申請す
ることが重要です。
2.個人・法人区分の決定
古物商許可を取得する際、個人名義で申請するか法人名義で申請するかを事前に決
定する必要があります。どちらの許可においても中古品の売買を行えるものの、名
義の違いによって運営の仕方や手続きが大きく異なるためです。
個人名義で許可を取得する場合は申請時の書類が法人よりも少なく、比較的手軽に
許可を取得できます。ただし、個人で取得した許可を法人で使用することは法律上
認められておらず、個人名義から法人名義への変更も不可となっているため、法人
として古物営業を行う場合は新たに法人名義で許可を取得しなければなりません。
もしビジネスとして⾧期的に古物販売を行いたい場合は、法人名義で許可を申請す
るとよいでしょう。手続きは個人許可よりも複雑ですが、信用度が向上し、資金調
達や取引の幅が広がるメリットがあります。
3.取り扱い品目の決定
個人・法人区分が決定したら、自身のビジネスで取り扱いたい品目について検討し
ます。古物営業法で分類されている品目は以下の13種類です。
・美術品類(絵画、彫刻、工芸品など)
・衣類(洋服、着物、布団など)
・時計・宝飾品類(時計、アクセサリー、眼鏡など)
・自動車(車両本体、タイヤ、カーナビなど)
・自動二輪車および原動機付自転車(バイク本体、部品など)
・自転車類(自転車本体、関連部品など)
・写真機類(カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡など)
・事務機器類(パソコン、コピー機、レジスターなど)
・機械工具類(家電、工作機械、ゲーム機など)
・道具類(CD・DVD、家具、日用品など)
・皮革・ゴム製品(バッグ、靴、毛皮など)
・書籍(文庫本、雑誌、漫画など)
・金券類(商品券、切手、収入印紙など)
複数の品目を選択することも可能ですが、必要以上に多くの品目を申請すると審査
が厳しくなる可能性があります。初回の許可申請時には、ひとまず1品目のみ選択
するとよいでしょう。
なお、取り扱い品目はのちに「変更届」で追加することも可能です。
4.警察署への事前相談
続いて、古物商許可を申請する警察署への事前相談を行いましょう。その際は自身
の居住地を管轄する警察署ではなく、古物商を扱う営業所の所在地を管轄する警察
署の「生活安全課 防犯係」に連絡します。
あらかじめ必要書類や手続きについて確認しておくことで、書類の不備や手続きの
ミスを防いでスムーズに許可を得ることが可能です。
5.必要書類の準備
警察署への事前相談で確認した内容をもとに、古物商許可申請に必要な書類を準備 します。個人名義と法人名義では必要書類が異なるため、事前にしっかりと把握し ておくことが大切です。
| 個人名義で申請する場合 | 法人名義で申請する場合 | |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 略歴書 | 必要(申請者本人と営業所の管理者のもの) | 必要(役員全員と営業所の管理者のもの) |
| 本籍が記載された住民票の写し | 必要(申請者本人と営業所の管理者のもの) | 必要(役員全員と営業所の管理者のもの) |
| 誓約書 | ||
| 身分証明書 | ||
| URLの使用権限を証明する資料 | 必要 | 必要 |
| 登記事項証明書 | 不要 | 必要(履歴事項全部証明書) |
| 定款の写し | 不要 | 不要 |
なお、許可申請書は管轄の警察署または各都道府県における公安委員会の公式サイ ト上で入手可能です。また、いずれの書類も「申請日から3か月以内」に取得する 必要がある点に注意しましょう。
6.書類の提出
再度管轄の警察署へ出向いてすべての書類を提出し、19,000円の申請手数料を納付 します。支払い方法は管轄の警察署によって異なりますが、現金または県の証紙に よる支払いが一般的です。
7.審査
申請が受理されると審査が開始され、通常約40日程度で結果が通知されます。場合 によっては、この期間中に警察官による営業所の立ち入り調査が実施されることも あります。
8.許可証の交付
審査が無事に終了した旨の連絡を受けたら、申請者は管轄の警察署に身分証明書を
持参して許可証を受け取ります。なお、許可証交付後は営業所に許可証を掲示する
義務があるほか、古物台帳を準備して適切に取引記録を管理する必要があります。
また、インターネット販売を行う場合は、許可証の番号をサイト上に表示しなけれ
ばならないため、忘れずに行いましょう。
法人設立にあたって登記先住所をお探しなら
「バーチャルオフィス」がおすすめ!
会社を設立してリユース販売事業を運営する場合は法人登記手続き時に「事務所の
所在地」を申請する必要がありますが、賃貸オフィスを借りるとなると高額な費用
がかかります。そこで、もし個人での活動がメインの場合や「なるべく費用を抑え
て設立したい」とお考えの場合はバーチャルオフィスを活用するとよいでしょう。
バーチャルオフィスとは登記申請可能な住所を貸し出しているサービスで、自宅を
拠点に事業活動を行う個人経営者やスタートアップ企業などから人気を集めていま
す。物理的な個室スペースを占有できるサービスではないことから、古物商の営業
所としては申請できませんが、法人登記時に「本店所在地」として申請することは
可能です。
なお、バーチャルオフィスを利用するメリットとしては主に以下の3点が挙げられ
ます。
【メリットその1】オフィスコストを抑えられる
賃貸オフィスを借りる場合、毎月高額な家賃を払い続ける必要があるほか、契約時 に家賃半年~1年分ほどの初期費用もかかります。しかし、バーチャルオフィスの 月額利用料は数千円程度、契約料も5,000円~10,000円ほどと非常に安価であり、経 済的にゆとりを持たせた状態で事業活動をスタートすることが可能です。
【メリットその2】自宅住所と事業用住所を分けられる
事務所所在地をバーチャルオフィスの住所にすれば、自宅兼オフィスで活動する場
合に自宅住所と事業用住所を分けられる点もおすすめポイントです。自宅の住所が
事業用住所を兼ねる場合、自宅の引越し時に登記変更手続きを行って新しい事業用
住所を申請する必要がありますが、初めから分けておけばその手間を省けます。
また、自宅が賃貸物件の場合はそもそも登記先住所として申請できないことが多い
ため、登記可能な住所をお手頃価格でレンタルできるバーチャルオフィスの存在が
大いに役立ちます。
【メリットその3】自宅のプライバシーを守れる
契約形態によっては自宅の住所で法人登記を行える場合もありますが、自宅のプラ
イバシーが脅かされるリスクがある点に注意が必要です。登記申請した住所は国税
庁の「法人番号公表サイト」に掲載されるほか、本店所在地として自社の公式サイ
トや名刺上にも表示させる必要があり、自宅住所が不特定多数の人に知られてしま
います。
バーチャルオフィスの住所で申請すれば、自宅のプライバシーがしっかりと保護さ
れ、安全性の高い環境でビジネス活動を進められるでしょう。
まとめ
個人・法人問わず、「古物営業」にあたる場合は古物商許可の取得が必要です。
まずは申請要件を確認し、個人・法人区分や品目について慎重に検討したうえ
で、古物商を扱う営業所の所在地を管轄する警察署にて申請手続きを行いま
しょう。
なお、バーチャルオフィスを活用すれば、自宅を拠点としてリユース販売事業
を行う場合に自宅住所と事業用住所を分けることが可能です。少ないコストで
安全性の高い事業環境を整備できるため、法人名義で古物商許可を申請したい
方はぜひ導入を検討するとよいでしょう。
記事を探す
- 03局番電話番号
- ChatGPT
- FAT
- IT導入補助金
- M&A
- NPO法人
- SDGs
- ものづくり補助金
- アンケート
- インバウンド
- オンライン秘書サービス
- クラウドファンディング
- コワーキングスペース
- サイン証明書
- サスティナブル
- シニア起業
- テレワーク
- トラブル
- トランクルーム
- ドッグトレーナー
- バーチャルオフィス
- ビザ
- フリーランス
- フリーランスの節税
- ベンチャーキャピタル
- ペットシッター
- ペットホテル
- マイクロ法人
- マンション建て替え
- マンション敷地売却制度
- リユース販売事業
- レンタルオフィス
- レンタルスタジオ
- ローン
- ワーケーション
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 不動産投資
- 不動産投資コンサルタント
- 中小企業診断士
- 事業再構築補助金
- 事業売買
- 事業継承
- 会社設立
- 会社設立72時間
- 個人事業主
- 副業
- 創業支援
- 助成金
- 労務
- 古物商
- 商標権
- 商標登録
- 国際法務
- 国際税務
- 土地家屋調査士
- 地方創生
- 地方在住
- 地方移住
- 増資
- 士業
- 変更登記
- 外国人
- 外国人留学生の起業
- 女性起業
- 子会社
- 学生起業
- 定款作成ツール
- 審査
- 小規模事業者持続化補助金
- 就労ビザ
- 弁理士
- 役員住所変更
- 役員変更
- 役員氏名変更
- 後継者
- 日本支店
- 日本進出
- 東京都あきる野市
- 東京都三鷹市コワーキングスペース
- 東京都三鷹市レンタルオフィス
- 東京都世田谷区コワーキングスペース
- 東京都世田谷区レンタルオフィス
- 東京都中央区コワーキングスペース
- 東京都中央区レンタルオフィス
- 東京都中野区コワーキングスペース
- 東京都中野区レンタルオフィス
- 東京都八王子市コワーキングスペース
- 東京都八王子市レンタルオフィス
- 東京都北区コワーキングスペース
- 東京都北区レンタルオフィス
- 東京都千代田区コワーキングスペース
- 東京都千代田区レンタルオフィス
- 東京都台東区コワーキングスペース
- 東京都台東区レンタルオフィス
- 東京都吉祥寺コワーキングスペース
- 東京都品川区コワーキングスペース
- 東京都品川区レンタルオフィス
- 東京都国分寺市コワーキングスペース
- 東京都国立市コワーキングスペース
- 東京都墨田区コワーキングスペース
- 東京都墨田区レンタルオフィス
- 東京都多摩市コワーキングスペース
- 東京都多摩市レンタルオフィス
- 東京都大田区コワーキングスペース
- 東京都大田区レンタルオフィス
- 東京都小平市コワーキングスペース
- 東京都府中市コワーキングスペース
- 東京都文京区レンタルオフィス
- 東京都新宿区コワーキングスペース
- 東京都新宿区レンタルオフィス
- 東京都日野市コワーキングスペース
- 東京都昭島市コワーキングスペース
- 東京都杉並区コワーキングスペース
- 東京都杉並区レンタルオフィス
- 東京都東久留米市コワーキングスペース
- 東京都東大和市コワーキングスペース
- 東京都板橋区コワーキングスペース
- 東京都板橋区レンタルオフィス
- 東京都江戸川区コワーキングスペース
- 東京都江戸川区レンタルオフィス
- 東京都江東区コワーキングスペース
- 東京都江東区レンタルオフィス
- 東京都清瀬市コワーキングスペース
- 東京都渋谷区コワーキングスペース
- 東京都渋谷区レンタルオフィス
- 東京都港区コワーキングスペース
- 東京都港区レンタルオフィス
- 東京都町田市コワーキングスペース
- 東京都町田市レンタルオフィス
- 東京都目黒区コワーキングスペース
- 東京都目黒区レンタルオフィス
- 東京都立川市コワーキングスペース
- 東京都立川市レンタルオフィス
- 東京都練馬区コワーキングスペース
- 東京都練馬区レンタルオフィス
- 東京都羽村市コワーキングスペース
- 東京都荒川区レンタルオフィス
- 東京都葛飾区コワーキングスペース
- 東京都葛飾区レンタルオフィス
- 東京都西東京市コワーキングスペース
- 東京都西東京市レンタルオフィス
- 東京都調布市コワーキングスペース
- 東京都豊島区コワーキングスペース
- 東京都豊島区レンタルオフィス
- 東京都足立区コワーキングスペース
- 東京都足立区レンタルオフィス
- 東京都青梅市コワーキングスペース
- 法人化
- 法人口座開設
- 法人成り
- 海事代理士
- 海外企業
- 海外在住
- 海外移住
- 特許
- 生成AI
- 登記情報
- 登記簿謄本
- 目的変更
- 相続
- 社会保険
- 社労士
- 私設私書箱
- 移転登記
- 第一種動物取扱業
- 節税
- 納税管理人
- 経営管理ビザ
- 自宅マンションで登記
- 自社所有拠点
- 著作権
- 融資
- 補助金
- 貸し会議室
- 費用相場
- 資産管理会社
- 資金調達
- 起業スクール
- 重任登記
- 閉鎖(廃業)
- 開業
- 電子帳票システム
- 電子帳簿保存法
- 駐在員事務所